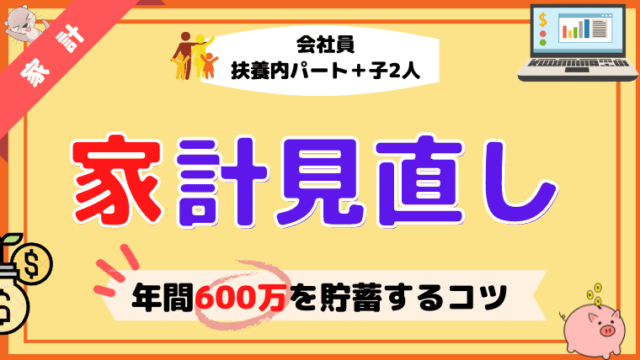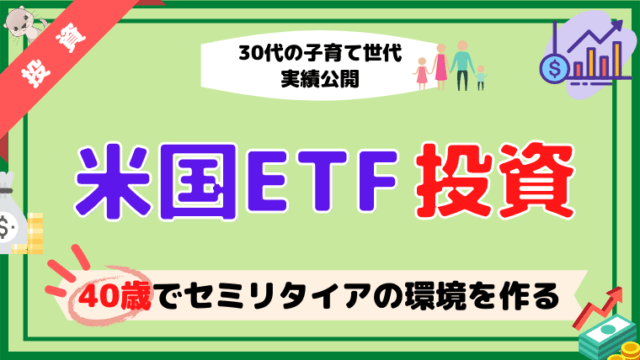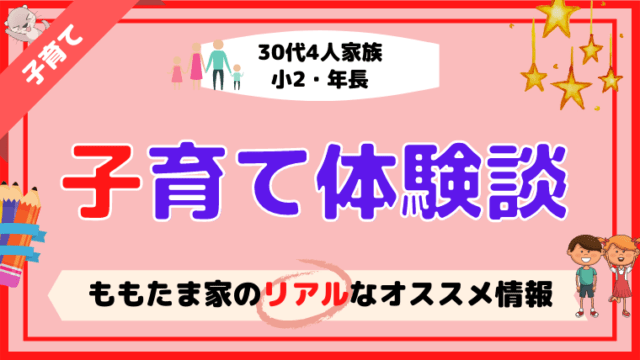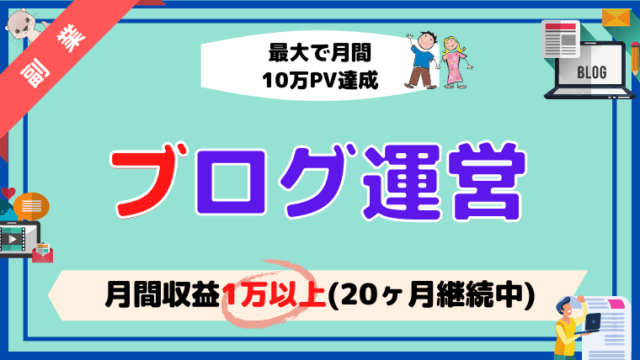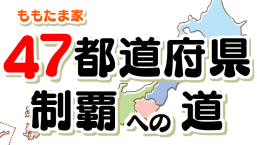- 賃貸でカブトムシを育てる
- カブトムシを育てるのに必要なグッズを知りたい
- カブトムシを家庭で飼育する体験談が知りたい。
こんにちは、ももたまです。
私達は2019年5月に近所の方からカブトムシの幼虫をいただき、これまで約1年、子供達と一緒に飼育してきました。
カブトムシのような虫でも、生き物に触れるという経験は子供達にも貴重な経験となっています。
それに、犬や猫などの動物と比べて虫の寿命は短いことが多いです。
子供達がカブトムシの死、そして産卵・羽化といった新しい命を、間近で実感できた1年でもありました。
そこで今回は、実際にカブトムシを飼育するためのグッズ、ポイントを体験談と共にまとめました。
具体的には、以下の6つの時期に分けてみていきましょう。
- 幼虫(1回目)
- サナギ(1回目)
- 成虫
- 産卵
- 羽化・幼虫(2回目)
- サナギ(2回目)
目次
カブトムシ飼育:幼虫(1回目)
カブトムシの幼虫の飼育方法と必要なもの

幼虫の時期は土が重要になるので、栄養のある土の中で育てていきましょう。
土も栄養剤も100均で購入できるので、簡単に準備することができます。
ただ、100均での販売は夏にしか行われないため、冬の分も合わせて購入しておきましょう。
幼虫を育てるために購入したものは5つで、全て100均で揃えました。
- 飼育用の透明ケース:300円
- 土:100円
- 栄養剤:100円
- 脱臭剤:100円
- コバエ取りシート:100円
土は腐葉土が含まれるので、脱臭剤を一緒に入れておくと室内でも匂いません。
また、コバエも湧くのでケースの上にコバエ取りシートもかかせませんね。
あとは定期的に以下の2つを行えば大丈夫です。
- 霧吹きでの水やり→土の乾燥を避けるため
- 土の入れ替え→土全体にウンチが増えて栄養が無くなるため
カブトムシの幼虫に対する子供達の様子

最初に飼育用ケースを作った時は大はしゃぎだった子供達。
ただ、幼虫は基本的に土の中なので、日に日に関心は薄れていきましたね。
それでも、定期的な水やりや土の入れ替えは、一緒に楽しんで取り組んでいました。
カブトムシ飼育:サナギ(1回目)
最初にもらった幼虫は1匹だけだったため、サナギの様子は観察できませんでした。
その代わり、2020年5月の今、ちょうどサナギ(2回目)になりかけています。
今回はしっかり観察してみようと子供達と楽しみにしています。
カブトムシ飼育:成虫
カブトムシの成虫の飼育方法と必要なもの

無事にカブトムシが成虫となり、飼育用ケースも成虫向けにしました。
必要なものは全部で4つでしたが、こちらも全て100均で購入することができます。
- 土:100円
- 餌:100円
- 餌置き場:100円
- 隠れる木など:100円
飼育も基本的には餌をあげて土の乾燥防止のために、定期的な水やりをするくらいです。
また、いただいた幼虫は雄(オス)でしたが、雌(メス)の成虫を友人からもらうことができました。
そのため、雄(オス)雌(メス)の夫婦としてカブトムシを飼育することができました。
カブトムシの成虫に対する子供達の様子

カブトムシが成虫になると、子供達も喜んで触ってお世話をしていましたね。
特に昆虫ゼリーを置いたり、水をかけたり、触って遊んだりと楽しそうな様子でした。
カブトムシ飼育:産卵
カブトムシの産卵の飼育方法と必要なもの

カブトムシ夫婦を1つのかごに入れて飼育していると、交尾の様子も見ることができます。
交尾の後、産卵のために水を少し多く含めた土を敷き詰めたケースに、雌(メス)だけを移動させます。
上手く交尾が出来ていれば、1週間ほどで土の中に写真のような卵を見つけることができます。
卵はスプーンで取り出し、田植えのように小さな穴を空けた土と一緒に別のケースに入れましょう。
ちなみ環境が整っていると、カブトムシの雌(メス)は卵を産めるだけ産みます。
ただし産卵は体力をとても消耗するため、寿命が短くなってしまうことも多いです。
産卵させたくないなら、通常の浅い土の環境で雄(オス)、雌(メス)一緒に飼ってもいいですよ。
カブトムシの産卵に対する子供達の様子
子供達が初めてカブトムシの卵を見た時は、嬉しさと驚きが入り混じったような様子でした。
当時3歳だった下の子は、とても不思議そうに小さな卵を見つめていましたね。
カブトムシ飼育:死去

どんな生き物でも、必ず死がやってきます。
カブトムシも動きが日に日に小さくなり、もうすぐ死ぬということを子供達に伝えていました。
そして、カブトムシが死んでしまった後、子供達と一緒にお墓を作りましたね。
子供が死を考えるキッカケともなり、夜寝るときに不安で泣いてしまうこともありました。
カブトムシの羽化・幼虫(2回目)
カブトムシの羽化の飼育方法と必要なもの

卵の間は、定期的に霧吹きで土を湿らせるくらいしか、やることはありません。
しばらくすると土の中を動く様子があったり、画像のように小さな幼虫が確認できます。
ちなみに、小さい幼虫同士が近くにいると共食いをすることがあります。
できるだけ場所を離したり、別々の容器で飼うということも選択肢に入れましょう。
私達は22匹のうち10匹を、同じく子育てしている友人達にプレゼントしました。
カブトムシの羽化、幼虫(2回目)に対する子供達の様子

子供達は幼虫がスクスクと成長していく様子を、喜んで見ていたのが印象的でした。
写真のように、大きさが子供たちの手くらいまで育つので、結構迫力がありましたね。
ちなみに、12匹もいるのでケース内はすぐにウンチで一杯になってしまいます。
そういう意味でも、子供達はお世話のやりがいを感じていましたね。
カブトムシのサナギ(2回目)
カブトムシのサナギ(2回目)の飼育方法と必要なもの

幼虫はサナギに向けて自分のスペースを作るため、4月位からは土を変えないようにします。
また、暗い所で幼虫たちを飼育していると、写真のようにケースの壁側でサナギになってくれます。
子供達と一緒にカブトムシの飼育に取り組んだ感想

実際に約1年、子供達と一緒にカブトムシを飼育してきましたが、本当に色々な経験をさせてもらいました。
正直な話ですが、飼育の間に子供達が喜んだり悲しんだりすることは本当にわずかな時間です。
それでも、生き物の死、そして新しい命が誕生するという一生を間近で体験できたことは貴重でした。
死んだ時は誰もが悲しく、新しい命の誕生には自然と嬉しさがこみ上げてくる。
そんな当たり前のことですが、普段の生活では実感できる機会が少ないです。
そういう意味でもカブトムシに限らず、生き物を飼うことは子供達にとって良い経験になります。
また、カブトムシは犬や猫などの動物に比べれば手間もかからず、費用も安いことは魅力ですね。
まとめ:カブトムシを子供と一緒に育ててみよう
今回はカブトムシの飼育について、方法やポイントを子供達との体験談と共にまとめました。
必要な道具は全て100均で揃えられ、賃貸や室内でも飼育することができます。
寿命が短いカブトムシだからこそ、生き物の生と死を身近に感じられる貴重な経験ができます。
もちろん、中途半端な意識で飼育を初めて欲しいとは思いません。
だからこそ、生き物を飼うことの大切さを、子供達と一緒に考えてほしいですね。